2018年7月に、相続法の見直しを内容とする「改正民法」が成立して公布されました。
約40年ぶりの相続に関する民法改正ですね。
民法には、亡くなった人(被相続人)の財産をどのように承継するかなど、基本的なルールが定められています。
これを「相続法」といいます。
2019年から2020年にかけて、改正が段階的に施工されました。
今回の改正は高齢化が進み、相続の環境変化に対応するような見直しになっています。
細かな内容はたくさんありますが、ここでは相続に関するポイントを見てみます。
「配偶者居住権」が創られました!
これだけ聞いてもなんのことか分かりませんよね・・・(+_+)
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に、亡くなった人(被相続人)が所有する建物に住んでいた場合、終身または一定の期間、その建物を無償で使用できる権利です。
【 ケーススタディ 】
例えば亡くなったお父さんが6000万の遺産(土地建物評価2500万、預金3500万)があったとします。
相続人が配偶者のお母さんと、娘さんの2人だとします。
基本的に法定相続分は1/2ずつですので、お母さんと娘さんは3000万ずつです。
ここでお母さんの住むところが無くなると困るので、評価2500万の土地建物を相続したとします。
そうすると、お母さんは評価2500万の土地建物と500万の預金、娘さんは3000万の預金・・・となります。
これではお母さん、これかの生活費が不安ですよね・・・。
※(注)基礎控除や税額などの細かな計算は省略した概要です!
このような場合のために、居住用不動産の権利として「配偶者居住権」を設定します。
そうすることで、これまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産を多く取得できるようになり、その後の生活を安心して送ることができます。
特別の寄与!?
高齢化が進み、「介護」の問題が深刻化してきました。
収入確保のために共働きが多い昨今、誰が介護するのか、費用はどうするのか・・・。
日本の社会的な大きな問題ですよね。
今までは相続人以外の親族が、亡くなった方を介護しても、その費用(相続財産)をもらうことはできませんでした。
【 ケーススタディ 】
例えば亡くなったお父さんに、長男・次男・三男がいたとします。
ところが長男はお父さんが亡くなる前にすでに死亡しており、長男の奥様が亡くなったお父さんの介護につきっきりだったとします。
このような場合、今まではあくまで相続人は、次男と三男なので、かわいそうに・・・
長男の奥様は何一つ相続財産をもらうことはできなかったんですね・・・。
※代襲相続等は無しとしてます。
しかし、この度創られた制度は、相続人以外の親族が、無償で亡くなった方(被相続人)の介護や看病をした場合、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになったんですね。
今回のケースの長男の奥様は、遺産を相続した次男と三男に対して、金銭の請求ができるんです。
ただし、寄与分や特別寄与の金額や割合は原則として請求者と相続人との協議にて決定されます。
あまり、現実的じゃないですよね・・・。
協議で定められない場合は相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内限り、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことができます。
これはもう普通の方がご自身でできる内容ではありませんので、早めに税理士や法律事務所に相談されるのをお勧めします。
とはいえ、この制度は現状認められないケースも少なくないようです・・・。
そのような場合に備えてお世話をしてくれた方等へ財産を残したい場合は、元気なうちに生前贈与や遺言書を作成するなどの対策をしておくことも重要ですね。
法務局で遺言を保管できる!?
「遺言」というと、なにか特別な感じがしますが、高齢化を迎え、また相続財産の中で不動産が減ってきたことを考えると、今後、遺言が増えてくるかもしれません。
本人が自分で書く遺言を「自筆証書遺言」といいます。
「自筆証書遺言」を作成した人は、法務大臣が指定する「法務局」に遺言書の保管を申請できます。
封印してある遺言書を開封して中を見るには「家庭裁判所」の検認が必要ですが、法務局に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認が不要となったんですね。
これで、より「遺言」が作成する側も、将来の相続人にとっても身近な手続きになりました。
民法の改正は様々な内容がありますが、相続の中で特に注目の改正をあげました。
支えの壁になってくれていた親が亡くなったとたんに、潜んでいた問題が吹き出します。
相続だから争いがおこるのではなく、相続で争いが吹き出すんですね。
過去にすでに贈与した財産はあるのか?
将来の介護の問題をどうするのか?etc・・・
ご自身の財産すべてを見渡して、相続人にどう振り分けて相続するのがいいのか考える必要があります。
そして、それを「遺言」で残しておくと理想的です。
相続人に関して言うと、法定相続分であれば、先に渡した財産である特別受益や、介護などの寄与分を考慮して、客公平な分割ができます。
しかし、何が遺産の先渡しで、何が寄与にあたるのか・・・その意見が食い違い、遺産分割で争う可能性もあります。
今回の民法の改正は、高齢化や社会環境を踏まえて、様々な立場の人を考えた改正になっています。
ポイントを押さえて、相続が始まる前に、争いにつながりそうな問題を親族間で話し合い、解決しておくことをおすすめします。

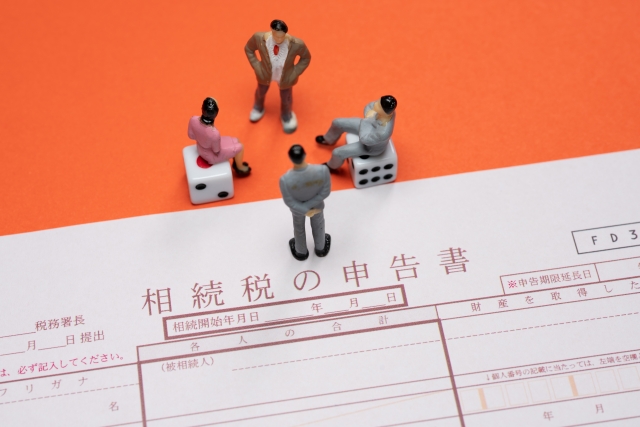






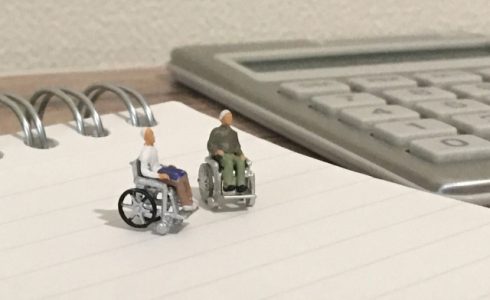


この記事へのコメントはありません。